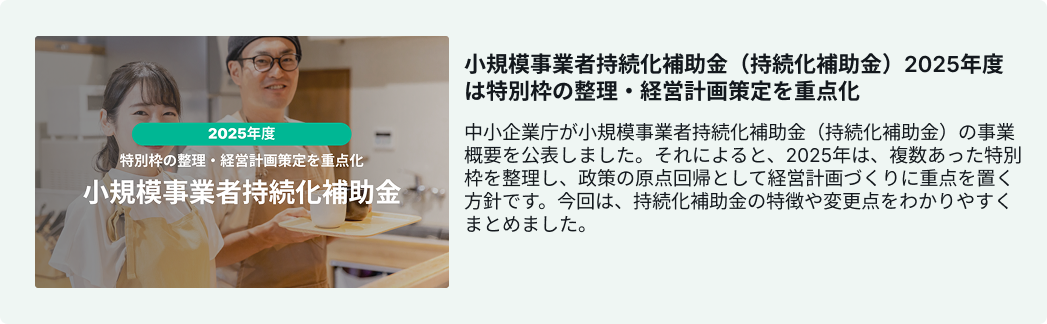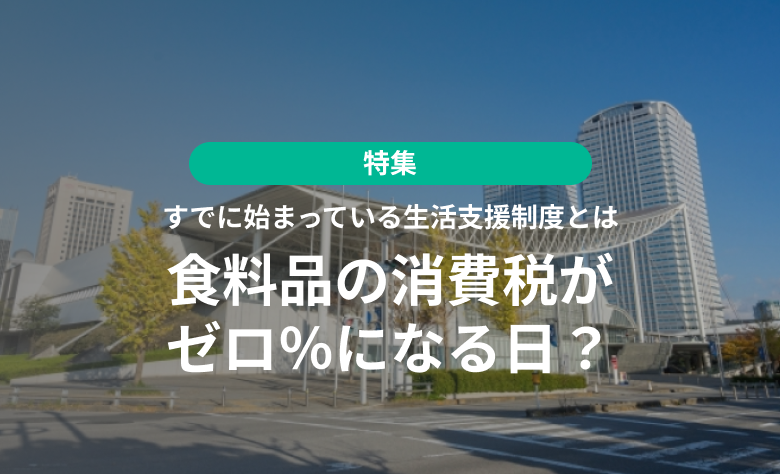
「食料品の消費税を0%に」といった声が、ニュースやSNSなどを通じて注目を集めています。物価高が続く中で、家計への影響が深刻化し、日々の食費に悩む家庭も少なくありません。そうした背景から、政府や自治体は生活費や食費の負担を軽減するため、さまざまな支援策を講じています。
こうした支援制度の中には、対象者が所得や生活状況によって限定されるなど、すぐに活用できるとは限らないケースもありますが、制度の全体像を知っておくことは、将来必要になったときの備えとして重要です。今回は、「消費税0%」の議論に先立ち、現在展開されている代表的な生活支援策を紹介します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次
なぜ「食料品消費税0%」が求められているのか?
ここ数年、エネルギー価格や原材料費の上昇により、あらゆる物の値段が上がっています。特に食料品は生活に欠かせないものであるため、価格上昇の影響を受けやすく、家計への圧迫も大きくなりがちです。さらに、毎日のように購入する食料品には消費税が課されており、積み重なれば大きな負担になります。
こうした背景から、「食料品だけでも消費税をなくすべきではないか」という声が、SNSや報道を通じて広がりをみせています。海外でも、イギリスやカナダなどの国では一部の食料品に対してゼロ税率が適用されており、日本でも同様の対応を求める意見がみられます。
さらに、国内でも政治的な議論が進みつつあります。NHKの報道によると、自民党参議院側では消費税の税率引き下げを求める声が約8割にのぼり、公明党も食料品の税率引き下げを選択肢の一つとする考えを示しています。一方、立憲民主党は「時限的な食料品の消費税率0%」と「給付付き税額控除」への移行案を軸に調整を進めており、維新や国民民主など他の野党も引き下げを主張しています。
参考:NHK NEWS WEB 消費税扱いで与野党議論活発に 引き下げや時限的になくす意見
ただし、消費税の見直しには、財源確保や制度設計といった大きな課題が伴い、短期間で実現するのは難しいのが現状です。そのため、現時点では「いつか実現するかもしれない制度」に期待するだけでなく、すでに始まっている支援制度を知り、必要な場面で活用できるよう備えておくことが現実的な選択肢といえます。
実質「食費支援」になる代表的な制度一覧
ここでは、給付金、生活困窮者向けの支援制度、さらには地域NPOやフードバンクの活動など、生活の負担を軽くするために活用できる代表的な支援策を紹介します。(1)地方自治体の物価高騰対応給付金
令和6年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、政府は、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対して3万円、さらに18歳以下の子ども1人あたり2万円を給付する方針を示しました。これを受けて、各自治体では「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、対象世帯への給付事業を実施しています。
たとえば東京都江東区では、「江東区物価高騰重点支援給付金」として、該当する世帯に支援金を支給しています。これらの支援金は、食費や光熱費など日常生活の負担軽減に役立つものです。
| 支援対象:江東区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯 支援内容:住民税非課税世帯への3万円および子ども1人あたり2万円の給付 |
対象世帯には「ご案内」または「申請書」が送付されています。「ご案内」が届いた場合、記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する手続きは必要ありません。「申請書」が届いた場合は、必要事項を記入し、必要書類とともに返信用封筒にて返送します。申請期限は、令和7年5月30日(金)までです。申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。
(2) 生活困窮者自立支援制度
「生活困窮者自立支援制度」は、経済的な理由で最低限度の生活を維持することが難しくなるおそれのある方を対象に、包括的なサポートを行う制度です。現在生活保護は受けていないものの、生活保護の対象となる可能性があり、かつ自立の見込みがある方が対象です。支援の窓口となるのは全国の自治体に設置されている「自立相談支援事業所」で、生活に関する悩みを幅広く受け付けています。
以下のような支援を通じて、自立に向けた生活の再建をサポートします。
| ・一時生活支援:住まいや収入がなく生活が極めて困難な方への宿泊・食事の提供 ・自立相談支援:生活や経済的な困難についての相談を受け、状況に応じた支援計画を作成 ・住居確保給付金:離職や収入減で住居を失うおそれのある方への家賃支援 ・就労準備支援/就労訓練:すぐに働くのが難しい方への段階的な就労支援 |
生活困窮者自立支援制度は、日常的に誰もが利用するような支援とは言えませんが、「どうにもならない」と感じたとき、こうした公的支援の選択肢があるということを知っておくことは大切です。
(3) フードバンク・地域NPOの取り組み
「フードバンク」や地域NPOによる食料支援は、食品の無償提供を通じて、さまざまな家庭の食費負担を軽減する取り組みです。生活に困窮する方々が税制の変更を待たずに利用できる、実質的な「食費支援」といえます。
| 【フードバンクちば(千葉県)】 企業や個人から提供された食品を、生活に困っている方々へ無償で届ける活動を行っています。食品の寄付も随時受け付けています。 参考:フードバンクちば |
| 【フードバンク渋谷(東京都渋谷区)】 地域のひとり親家庭や外国人家庭、障がい者世帯などに対し、食品の提供を実施しています。「食の先の支援」として、行政サービスや他団体との連携も行っています。 参考:フードバンク渋谷 |
| 【フードバンクTAMA(東京都多摩地域)】 児童福祉施設や子ども食堂、ひとり親家庭への食品支援を行い、顔の見える支援を心掛けています。企業や農家、個人からの食品寄贈も受け付けています。 参考:フードバンクTAMA |
これらの団体では、食品の提供を希望する方や、食品の寄付を希望する方からの問い合わせを受け付けています。詳細は、各団体の公式サイトをご確認ください。
実は企業も支援を受けている?〜食品価格抑制を助ける制度
食品価格の高騰は消費者の家計を圧迫する一方で、飲食業や食品販売などの事業者側にも原材料費や光熱費の上昇という形で重くのしかかっています。そこで、一部の自治体では中小企業向けの支援制度が導入されています。こうした施策は、間接的に食品価格の安定化につながる取り組みといえます。
長野県御代田町「事業者向け原油価格・物価高騰対応給付金」
長野県御代田町では、原油価格・物価高騰の影響により経済的に影響を受けている町内事業者の経営支援を目的として、給付金を支給します。
- 対象者:飲食サービス業、宿泊業、運輸業、郵便業
- 支援内容:給付金30万円
参考:御代田町 「事業者向け原油価格・物価高騰対応給付金」の支給について
鹿児島県「食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業補助金」
鹿児島県では、県内食品関連製造業者の生産性を高め、競争力の強化を図るため、生産工程の自動化・省力化等による生産効率の向上や新たな需要獲得に必要な機械装置の導入等の取組を支援しています。
- 対象者:県内に事業所を有する食品関連製造業を営む中小企業者
- 支援内容:既存の生産工程の省力化や生産能力の増強等のための機械装置等の導入等に係る経費の一部を補助
参考:鹿児島県食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業
これらの支援は、直接的に食品価格を下げるものではありませんが、事業者の経営環境を整えることで、価格の安定につながる可能性があります。間接的ではあるものの、結果的に消費者にとっても負担を感じにくい仕組みづくりの一端を担っているといえるでしょう。
まとめ
今回紹介した支援制度の多くは、所得要件のあるものや事業者向けが中心で、誰もがすぐに使えるとは限りません。とはいえ、物価高の中でどういった支援策があるのかを知っておくことは、将来の選択肢を広げることにもつながります。消費税の引き下げを待つだけでなく、今ある制度の全体像を知ることから始めてみましょう。支援策の動向に注目しつつ、自分に合った支援が始まったときにスムーズに活用できるよう備えておくことが重要です。
おすすめリンク・参考情報
以下に、生活支援制度や食料支援に関する参考情報をまとめました。ご自身やご家族の状況に応じて、活用できる制度があるかご確認ください。
【物価高騰などへの対応を含む経済対策の全体像(内閣府)】
国の支援制度は、個別の給付金や補助金・助成金だけでなく、経済全体を支える包括的な対策の中で実施されています。内閣府のサイトでは、政府が策定した最新の経済対策の概要や資料を確認できます。
▶内閣府|経済対策等
【フードバンク検索】
お住まいの地域で食品支援を受けたい方や、食品の寄付を検討されている方は、以下の情報をご参照ください。地域の活動団体を掲載しています。
▶消費者庁|フードバンク活動等
【生活困窮者支援窓口一覧(市区町村別)】
生活にお困りの方に向けて、全国の自治体に設置された自立相談支援機関の窓口情報をまとめた一覧です。支援の入り口として活用できます。
▶困窮者支援情報共有サイト〜みんなつながるネットワーク〜|自立相談支援機関 相談窓口一覧