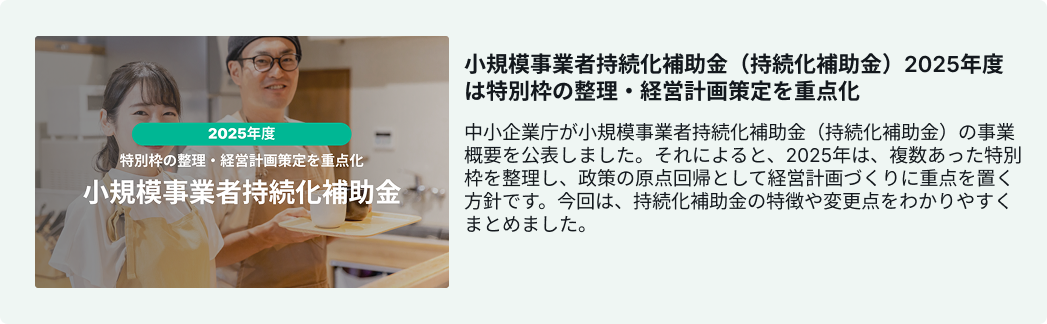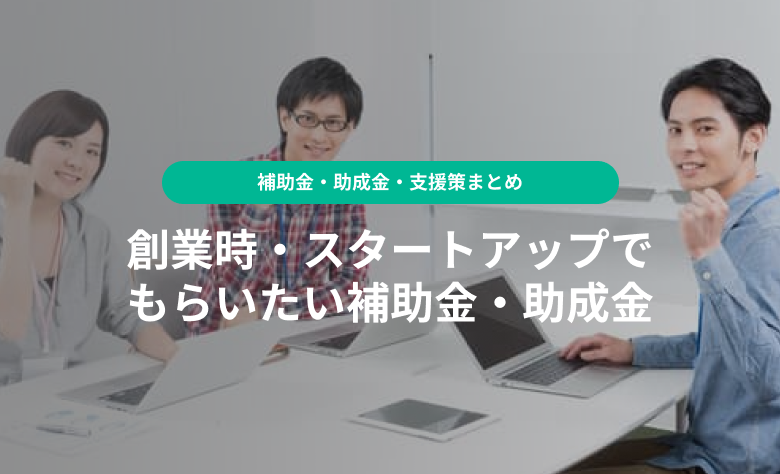
全国には、創業初期に活用できる補助金や助成金制度などが多数あります。創業初期の費用面での不安を解消できるよう展開されているため、自社の事業成長に集中したい方はぜひ活用しましょう。
今回の記事では各地域で使える補助金や助成金制度について紹介します。他にも制度は多数存在するため、気になる方はチェックしておきましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次
創業時にもらえる補助金・助成金のメリットとは
創業時には、初期費用や設備費、人件費、毎月の賃料など幅広い資金が必要です。創業初期の限られた売上からこうした資金を工面するのは苦労します。さらに、金融機関から融資を受けたとしても返済時は利子が発生するため、いずれにしても創業者の負担は増えるでしょう。
創業時に活用できる補助金や助成金制度を活用することで、こうした創業初期にかかる費用面をサポートしてもらえます。制度によっては融資返済時の利子も負担してくれるため、資金面の不安を減らし事業に専念したい方は、支援事業の利用を検討してみてください。
創業時にもらえる補助金・助成金
創業時にもらえる補助金や助成金制度について、今回は2024年7月時点で確認できた制度を紹介しています。補助金の情報は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は、公式ウェブサイトをご確認ください。東京都「創業助成事業」
【補助対象者】
都内での創業を具体的に計画している個人あるいは創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定要件を満たす方
【申請受付期間】
2024年9月25日~10月4日 *必着
【補助対象経費】
・事業費(賃借料や広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費)
・人件費(従業員人件費)
・委託費(市場調査や分析費)
【補助率および上限額】
下限額100万〜上限額400万円
※事業費および人件費を助成対象とする助成金の上限額300万円
※委託費を助成対象とする助成金の上限額100万円
▼東京都「創業助成事業」の詳細はこちらから
各地の創業補助金関連一覧
ここからは「J-Net21 | 創業者向け補助金・給付金(都道府県別)」を参考に、各道府県から代表的な制度をひとつずつピックアップしています。詳細はJ-Net21のサイトをご確認ください。
基本的には以下の項目をピックアップしています。
- 補助対象者
- 申請受付期間
- 補助対象経費
- 補助率および上限額
- 公式サイトのリンク
ただし、制度によっては項目が設定されていなかったり公式サイトに記載がなかったりするため、あらかじめご了承ください。
北海道札幌市「さっぽろ新規創業促進補助金」
【補助対象者】
・事業を営んでいない個人あるいは開業届の提出から5年を経過していない個人事業主で、新たに会社を設立した者である
・札幌市より特定創業支援等事業の証明を受けた後、登録免許税を支払っている
・札幌市内に登記上の本店所在地を置いている 等
【申請受付期間】
2024年4月1日~2025年3月31日 *必着
【補助率および上限額】
・株式会社設立の場合:一律17万5,000円(登録免許税7万5,000円+定款認証手数料相当分10万円)
・合名会社、合資会社、合同会社設立の場合:一律8万円(登録免許税3万円+定款認証手数料相当分5万円)
北海道札幌市「さっぽろ新規創業促進補助金」
https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/sinkisougyouhojyo.html
青森県十和田市「十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金」
【補助対象者】
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人
【補助対象経費】
外装や内装、設備等の工事に必要な経費
【補助率および上限額】
・補助率
1/2(1,000円未満は切り捨て) *商店街地区に限り2/3
・上限額
1:令和4年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積が200平方メートル以上で「上限額300万円」
2:現在市外に住所がある個人あるいは本店を持っている法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定である
営業に係る床面積が200平方メートル未満で「上限額150万円」
・その他
面積にかかわらず「上限額50万円」
青森県十和田市「十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金」
https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/koyou/sougyoushien.html
宮城県石巻市「石巻市創業支援補助制度」
【補助対象者】
・新規創業の場合:申請日時点で創業から1年を経過していない、あるいは創業予定の個人、個人事業主、会社、企業組合、協業組合、NPO法人
・第二創業の場合:申請日時点で事業承継から1年を経過していない、あるいは承継予定の個人事業主、会社、NPO法人
【申請受付期間】
随時申請可能ですが、申請書受理日が設けられています
申請書受理日:12月13日まで
【補助対象経費】
・人件費
・事業費(起業や創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費や店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費)
・委託費
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・補助金額:100万円以内
宮城県石巻市「石巻市創業支援補助制度」
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10451000/8300/20141008185052.html
秋田県横手市「横手市起業・創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・新たに起業する市内に住所がある個人または市内に主な事業所を持つ法人
・事業計画が明確であり、起業の実現性が高い事業である 等
【申請受付期間】
2024年4月1日~2025年1月31日
【補助対象経費】
・店舗工事費
・店舗の賃貸に係る礼金
・事業に必要な機械等設備費 等
【補助率および上限額】
・補助対象経費の1/3以内で上限額50万円
・秋田県外から移住して起業する場合は、1/2以内で上限額80万円
・ICTに特化して起業する場合は、1/2以内で上限額100万円
秋田県横手市「横手市起業・創業支援事業補助金」
https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1001359/1009098.html
山形県酒田市「酒田市開業支援補助金」
【補助対象者】
・酒田市内で令和6年3月31日までに創業予定の方
・要綱で定められた業種に該当する方
・補助金申請時点において納付期限の到来した市税を完納している方
・酒田市産業振興まちづくりセンターの支援を受けた方
【申請受付期間】
2024年4月1日~2025年2月末日まで
【補助上限額】
創業融資の完済までに係る利子相当額とし、上限額50万円
山形県酒田市「酒田市開業支援補助金」
https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/sogyo/startup-follow_up.html
福島県福島市「創業応援利子補給事業」
【補助対象者】
・対象融資の実行時において新たに創業する方、第二創業する方または創業後1年以内の方
・福島県信用保証協会の保証対象となる事業を営む方
・市内に新たに事業所を設置する法人または個人の方で、引き続き市内で事業を営むことが確実な方 等
【補助対象の利子】
創業にかかる融資の利子全額
【補助対象の融資および上限額】
・補助対象の融資
「福島県起業家支援保証融資」
「株式会社日本政策金融公庫国民生活事業における創業向け融資」
「市内民間金融機関が実施する融資であって、前号の融資の標準的な条件に準じるものとして市長が特別に認めた融資」
・上限額:2,000万円
福島県福島市「創業応援利子補給事業」
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/syoukougyou-plaza/shigoto/chushokigyo/shien/ouennrisi.html
栃木県真岡市「真岡市新製品開発・販路開拓支援補助金」
【補助対象者】
市内において操業あるいは事務所等の設置から3年以内の中小企業者で、新製品開発や販路開拓を行う者
【申請受付期間】
随時受付中 ※2023年4月~2028年3月(5年間)
【補助対象経費】
・大学および研究機関等との共同開発に係る経費(負担金)
・原材料および副資材の購入に係る経費(原材料費)
・設備および機械装置の購入やリースに係る経費(工事請負費や備品購入費、使用料、賃借料) 等
【補助率および上限額】
・補助率:1/2
・上限額:30万円
栃木県真岡市「真岡市新製品開発・販路開拓支援補助金」
https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/shokokanko/gyomu/sangyo_shinko/shokogyo/5525.html
群馬県富岡市「創業者スタートアップ応援事業補助金」
【補助対象者】
・市内において新たに創業する者あるいは申請時に創業日から2年を経過していない
・市内に新たに本店および主な事業所を設置する法人
・個人事業主の場合、市内に住所があり、かつ新たに主な事業所を設置する個人
・特定創業支援事業に該当するスクールの受講者 等
【補助対象経費】
・備品購入費(備品の購入費やリース料)
・広告宣伝費(広告やチラシの製作、配布に必要な費用)
・商業登記費(個人事業主の場合は商業登記に必要な費用。法人の場合は設立登記に必要な費用)
・改修や改築費(郊外の空き店舗や空き家の改修、改築および附帯設備の設置に必要な経費)
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:10万円〜
群馬県富岡市「創業者スタートアップ応援事業補助金」
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1560235064289/index.html
埼玉県熊谷市「熊谷市創業者応援補助金」
【補助対象者】
・市税の滞納がない
・市内に事業所を設置し、あるいは設置しようとしている
・創業後、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種を営んでいる 等
【補助対象経費】
・事業所内外装工事費(外壁塗装や看板設置、クロスなど)
・広告宣伝費(ホームページ作成や広告掲載料など)
【補助率および上限額】
・補助率:1/2
・上限額:20万円
埼玉県熊谷市「熊谷市創業者応援補助金」
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/jigyousya/sogyosyashien.html
千葉県茂原市「茂原市創業支援補助金」
【補助対象者】
・市内において補助金の申請年度内に創業を行う、または申請時に創業日から5年を経過しない
・創業日に市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人
・市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている方 等
【補助対象経費】
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備または備品購入費 等
【補助率および上限額】
・補助率:補助対象経費1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
・限度額:30万円
千葉県茂原市「茂原市創業支援補助金」
https://www.city.mobara.chiba.jp/0000002218.html
神奈川県伊勢原市「創業準備奨励金」
【補助対象者】
以下の「特定創業支援等事業」の経営指導を受けた(または受ける見込み)創業者が対象です
・平塚信用金庫による特定創業支援等事業 「創業ハンズオン支援」
・中栄信用金庫による特定創業支援等事業 「創業ハンズオン支援」
・中栄信用金庫による特定創業支援等事業 「創業塾」
・中南信用金庫による特定創業支援等事業 「創業窓口相談」
【申請受付期間】
店舗の開店日等から3ヶ月の経過日まで
【補助対象経費】
空き店舗等を活用する場合に必要な改装費や広告宣伝費、備品購入費等
【補助率および上限額】
・補助率:補助対象経費の30%以内
・上限額:50万円
神奈川県伊勢原市「創業準備奨励金」
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2016112900051/
新潟県柏崎市「かしわざき創業者支援補助金(特定創業者の場合)」
【補助対象者】
・「柏崎・社長のたまご塾」または柏崎商工会議所や柏崎市商工会、柏崎信用金庫、第四北越銀行の個別特定創業支援を修了し、創業計画を作成した方
・特定創業支援を受けた証明書の発行を受けた方
・上記修了後、6ヶ月以内に市内で創業した方
【補助対象経費】
創業から1年以内に行う広告宣伝および事務所や店舗の改装等に必要な経費
【補助率および上限額】
・広告宣伝費:全額(最大30万円)
・改装費等:1/2(最大30万円)
新潟県柏崎市「かしわざき創業者支援補助金(特定創業者の場合)」
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/shogyokankoka/2/17/6625.html
富山県上市町「上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金」
【補助対象者】
上市町商工会が認定した事業計画に基づき、中心市市街地に位置する空き店舗等を活用した小売業や飲食業、サービス業、その他これらに類する事業の出店
【補助対象経費】
・店舗改修に係る経費(修繕費や工事請負費、備品購入費)
・賃借料(店舗が賃借の場合)
【補助率および上限額】
・店舗改修の場合
補助率:1/3以内(すべて町内業者を利用した場合は1/2以内)
上限額:100万円(すべて町内業者を利用した場合は150万円)
・賃借料の場合
補助率:2/3以内
上限額1年目:5万円、2年目:3万円
富山県上市町「上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金」
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1884.html
石川県小松市「小松市起業家支援利子補給事業補給金」
【補助対象者】
・新たに市内で事業開始するための具体的な計画を持つ有する方(開業後1年未満の者を含む)
・平成28年4月1日以降、金融機関から起業の融資を受けている方
・主な事業所を市内に置いている方
・市税完納者である
【申請受付期間】
貸付日から起算して1年を経過した後、3ヶ月以内に申請する
【補助対象経費】
貸付を受けた資金に係る利子支払額
【補助率および上限額】
貸付日の翌日から起算して、1年経過日までの間における利子支払額(上限額は10万円)
石川県小松市「小松市起業家支援利子補給事業補給金」
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1018/shoukoushinkou_monodukuri/8/1301.html
福井県敦賀市「敦賀市まちなか創業等促進支援事業」
【補助対象者】
・新しく創業しようとする方
・業態転換や新事業、新分野に進出する第二創業をする方
・多店舗化しようとする方
【補助対象経費】
重点地域での創業等における建築や設備工事費、備品購入費の経費
【補助率および上限額】
・補助率:1/3
・上限額:50万円
福井県敦賀市「敦賀市まちなか創業等促進支援事業」
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/business/kigyo/machisougyou.html
山梨県身延町「身延町創業支援等事業費補助金」
【補助対象者】
・町が実施する特定創業支援等事業を受講し、町の証明を受けた
・町税および町債務を滞納していない
・暴力団員でない、あるいは暴力団員に関与していない 等
【補助対象経費】
・事業拠点費(店舗等の新築および改装にかかる経費)
・賃借料(店舗等の賃借に係る家賃)
・機械器具費(機械装置、車両運搬の購入費) 等
【補助率および上限額】
・補助率:1/2
・上限額:300万円〜
山梨県身延町「身延町創業支援等事業費補助金」
https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/shoukou/2021-0409-0937-28-sog.html
岐阜県高山市「高山市特定創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・特定創業支援を受けた証明書を持つ方
・高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方
・申請日において高山市内に住民登録があり、かつ今後も市内で居住意思がある方 等
【補助対象経費】
・設備資金(市内の店舗あるいは事務所開設に伴う工事費用など
・運転資金(研修費やマーケティング調査費、広告費など)
・その他(特別に市長が認める費用)
【補助率および上限額】
創業日までにかかった初期経費に補助率1/3(補助金申請時35歳未満の方は2/3)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助
岐阜県高山市「高山市特定創業支援事業補助金」
https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1005878.html
静岡県伊豆市「伊豆市創業者等支援事業補助金」
【補助対象者】
・創業をした個人、または法人(創業予定を含む)
・納期限の到来した市税を完納している
・暴力団員等でない 等
【補助対象経費】
事業を行なうために市内に新たに設置した事業所の家賃経費および設置工事経費
【補助率および上限額】
・家賃経費:家賃経費の1/2。上限額は「1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分」
・設置工事経費:設置工事経費の1/2。上限額は「50万円」
静岡県伊豆市「伊豆市創業者等支援事業補助金」
https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1004/4/2/771.html
愛知県豊橋市「起業支援事業費補助金」
【補助対象者】
・市内で起業してから1年以内であり、とよはし創業プラットホーム参画機関に事業計画の策定に係る指導・助言を受けており、起業後も同機関の指導や助言を継続的に受ける
・継続して本市に本店(個人事業主については住所)を持つ意思がある
・フランチャイズチェーンでない
・市税の滞納がない
【申請受付期間】
起業日から1年以内
【補助対象経費】
・1単位あたり10万円以上の設備および備品購入に係る経費
・広告宣伝に係る経費
・法人登記に係る経費
【補助率および上限額】
・補助率:対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)
・上限額:30万円
愛知県豊橋市「起業支援事業費補助金」
https://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm
三重県四日市市「四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金」
【補助対象者】
・本市内に本店を置く法人あるいは本市内に主な事業所がある個人
・創業後、3年を経過していない
・市税を滞納していない者 等
【補助対象経費】
補助対象事業にかかる費用のうち、広告宣伝費や委託費、事務費、その他市長の認める経費
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:15万円
三重県四日市市「四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金」
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1616904675200/index.html
滋賀県大津市「商業地魅力アップ支援事業補助金」
【補助対象者】
市内の商店街振興組合等
【補助対象経費】
委託料や謝礼、旅費等、工事請負費、原材料費、使用料、賃借料、広告料、消耗品費、通信運搬費、保険料、その他市長が必要と認めるもの
【補助率および上限額】
・補助率:1/2相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)
・上限額:40万円
滋賀県大津市「商業地魅力アップ支援事業補助金」
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/1390459408734.html
京都府福知山市「福知山市起業家支援事業補助金」
【補助対象者】
・福知山市内で新たに起業や創業を行う、あるいは起業や創業の実施後1年未満
・日本政策金融公庫、京都信用保証協会、福知山商工会議所、福知山市商工会、市内金融機関いずれかの推薦を受けている
・他の法人、団体等の代表および役員ではない 等
【申請受付期間】
2024年4月10日~2025年3月31日
【補助対象経費】
・ソフト事業:報償費や印刷製本費、通信運搬費、委託料
・ハード事業:工事請負費や備品購入費
【補助率および上限額】
・ソフト事業
補助率:1/2以内
上限額:20万円
・ハード事業
補助率:1/4以内
上限額:50万円
京都府福知山市「福知山市起業家支援事業補助金」
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/25/54942.html
大阪府泉大津市「泉大津市創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・本市内の店舗等で事業を営んでいる
・中小企業基本法第2条で定める者である
・週4日以上営業を行なっている
・市税を滞納していない
【申請受付期間】
創業日から起算して6ヶ月以内
【補助対象経費】
事業を営むための事業所に係る家賃補助
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:5万円(交付決定日の属する月の翌月から起算して12か月分を限度)
大阪府泉大津市「泉大津市創業支援事業補助金」
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/seisaku/tiikikeizaika/osirase/1557468646514.html
兵庫県姫路市「まちなか・商店街創業支援事業補助金」
【補助対象者】
まちなか(中心市街地)または商店街に新たに出店しようとする方 等
【補助対象経費】
内装設備工事費や広告宣伝費などの出店に必要な経費
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:50万円
兵庫県姫路市「まちなか・商店街創業支援事業補助金」
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000005743.html
奈良県五條市「五條市創業支援利子補給補助金」
【補助対象者】
・産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業を市内でするもの。および創業開始日から5年未満に本市が指定する融資を受けた
・中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
・住所地および事業所を持つ市区町村において、市区町村税の滞納がない
・この補助金対象となる融資金を償還している
【申請期間】
2月末日まで
【補助対象融資】
・株式会社日本政策金融公庫の場合:創業に関する融資資金
・奈良県の場合:創業支援資金
【補助率および上限額】
対象融資それぞれの利子(上限額は1,200万円)
奈良県五條市「五條市創業支援利子補給補助金」
https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/kankoshinko/3/2_1/7320.html
鳥取県境港市「境港市創業支援補助金」
【補助対象者】
・境港市税の滞納がない
・個人が創業する場合、創業日までに市内に居住し本市の住民基本台帳に記録されている 等
【補助対象経費】
事業拠点費や宣伝広告費、設立登記費
【補助率および上限額】
・補助率:1/2
・上限額:30万円(山陰以外からのIターン移住者は50万円)
鳥取県境港市「境港市創業支援補助金」
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=106327
島根県松江市「チャレンジショップ事業費補助金」
【補助対象者】
・地域商業の活性化に寄与するものである
・空店舗あるいは空家に出店する
・法人にあっては市内に本店の登記をしている。個人にあっては市内に主な事業所を持っている 等
【補助対象経費】
家賃や広告宣伝費、改修費
【補助率および上限額】
・家賃の補助率:1/2。上限額6万円
・広告宣伝費の補助率:1/2。上限額20万円
・改修費の補助率:1/2。上限額150万円
島根県松江市「チャレンジショップ事業費補助金」
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu_shokokikakuka/sangyoshinko/1/4380.html
岡山県笠岡市「笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金」
【補助対象者】
・市内に事務所を設置し、または設置しようとしている者である
・市内に住所を持つ者、あるいは第10条に規定する補助金の交付申請提出日の前日までに市内に住所を持つ者である
・十分な調査研究に基づく計画性があり発展見込みのある事業を起業する者である 等
【申請受付期間】
事業開始日の3か月前を目途に相談ののち、事業開始日の30日前までに申請
【補助対象経費】
・店舗等の新築や改装に係る経費
・機械装置および設備購入、修繕に係る経費 等
【補助率および上限額】
・新規創業者支援事業
補助率:都市機能誘導区域内での事業は2/3。それ以外は1/2
上限額:100万円
・空き店舗等活用事業
補助率:都市機能誘導区域内での事業は2/3。それ以外は1/2
上限額:100万円
岡山県笠岡市「笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金」
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/30/43091.html
広島県三次市「三次市起業支援事業補助金」
【補助対象者】
・市内に住所を持つ新規起業者で、20歳以上69歳以下の者
・交付申請時に納期限の到来した市税料等を完納している
・大企業者の出資率が1/2未満である 等
【補助対象経費】
・事務所の新築または増改築等施設整備に必要な経費
・備品、什器等に必要な経費
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:100万円
広島県三次市「三次市起業支援事業補助金」
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1548.html
山口県山口市「山口市UJIターン創業者支援補助金」
【補助対象者】
以下のいずれかを満たす方が対象です
・所得税法第229条に規定する開業の届出により本市で事業を開始する移住者または移住予定者
・本市で新たに会社を設立し、事業を開始する移住者または移住予定者
【申請期間】
随時
【補助対象経費】
・機械器具整備や購入費(事業実施に必要不可欠な作業機械、厨房機器、事務器具等の整備・購入に必要な経費)
・施設改修費(事業実施に必要不可欠な施設の内装改修、トイレ改修等に必要な経費)
【補助率および上限額】
・補助率:1/3
・上限額:50万円
山口県山口市「山口市UJIターン創業者支援補助金」
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/24462.html
徳島県石井町「石井町創業促進事業補助金」
【補助対象者】
・町内に事業所等を設け創業し、かつ町内に住所を持つ個人あるいは本社所在地を町内に持つ法人
・産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から、特定創業支援等事業による支援を受けた者 等
【補助対象期間】
補助金交付決定年度の4月1日から3月31日まで、かつ開業日あるいは法人設立日の前後6ヶ月以内
【補助対象経費】
・事業用の土地あるいは建物の購入費、または賃借料
・事業所の増改築あるいは改修に必要な経費
・設備あるいは備品の購入費 等
【上限額】
10万円
徳島県石井町「石井町創業促進事業補助金」
https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2017072700019/
香川県観音寺市「観音寺市創業者支援事業補助金」
【補助対象者】
・市税の滞納がない
・市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている
・この要綱に基づく補助金の交付を受けていない 等
【補助対象経費】
店舗等借入費や設備費、マーケティング費、広報費、事務手続費
【補助率および上限額】
・補助率:2/3
・上限額:30万円
香川県観音寺市「観音寺市創業者支援事業補助金」
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/13661.html
愛媛県八幡浜市「八幡浜市創業等支援事業補助金」
【補助対象者】
・補助金交付申請をする年度に、八幡浜市内において新規創業や第二創業、事業規模拡大を行う
・特定創業支援等事業の支援を受けた証明を受けているもの、あるいは交付申請年度内に証明を受けるもの
・八幡浜商工会議所や保内町商工会あるいは金融機関から指導および支援を受けた事業計画書を作成する 等
【補助対象期間】
交付決定日以降から年度内まで
【補助対象経費】
・工事および修繕に係る費用
・店舗等の借入に係る費用
・設備および備品等の購入に係る費用 等
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・上限額:新規創業100万円、第二創業50万円、事業規模拡大30万円
愛媛県八幡浜市「八幡浜市創業等支援事業補助金」
https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022032500035/
高知県香南市「香南市空き店舗対策事業費補助金」
【補助対象者】
・出店店舗が、自己所有の店舗でない
・店舗所有者と補助事業者が、同居の親族、出資額50%を超える親子会社等密接な関係にない
・国税や都道府県税、市町村税を滞納していない 等
【申請受付期間】
2024年4月1日~2025年3月中旬
【補助対象経費】
店舗改装費
【補助率および上限額】
・補助率:1/4
・上限額:50万円
高知県香南市「香南市空き店舗対策事業費補助金」
https://www.city.kochi-konan.lg.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/sangyoshinko/2/1/1425.html
福岡県福岡市「福岡市新規創業促進補助金」
【補助対象者】
・事業を営んでいない個人あるいは開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主
・福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方
・福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方
【申請受付期間】
~2025年3月31日まで *必着
【補助対象経費】
会社の設立に必要な登録免許税額
【補助額】
・株式会社設立の場合:一律7万5,000円
・合同、合名、合資会社設立の場合:一律3万円
福岡県福岡市「福岡市新規創業促進補助金」
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou_06.html
佐賀県嬉野市「起業チャレンジWelcome応援金」
【補助対象者】
嬉野市外に3年以上住んでいる方が嬉野市内に引っ越して2年以内に市内で起業する方 等
【申請受付期間】
交付対象理由が発生したときから60日以内あるいは令和8年3月31日のいずれか早い日までに、嬉野市移住促進応援金交付申請書および誓約書に、転入後の世帯全員の住民票を添えて提出する
【補助対象経費】
起業に必要な費用(敷金および人件費を除く)
【補助率および上限額】
・補助率:1/2
・上限額:100万円
佐賀県嬉野市「起業チャレンジWelcome応援金」
https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/teiju/ijuouenkin.html#kigyou
長崎県南島原市「南島原市創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・個人の場合は市民である。法人にあっては代表者が市民である
・市税の滞納がない
・補助金の交付年度の年度末(3月末)までに創業できる 等
【補助対象経費】
・土地代を除く事業所を新設する経費および既存の建物改修費
・創業する事業に必要な設備機器の購入費
【補助率および上限額】
・補助率:対象経費の30%(1,000円未満は切り捨て)
・上限額
世界遺産やジオパークに関連した新たな取り組みとして認められる事業は200万円
上記以外の事業は100万円
長崎県南島原市「南島原市創業支援事業補助金」
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0035679/index.html
熊本県水俣市「水俣市創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・補助金の交付申請を行う年度内に創業を行う
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、市長から特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明書の交付を受ける
・補助金の交付を受ける年度の末日までに、補助対象者が個人の場合は、水俣市内に居住することとし、補助対象者が法人の場合は、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと 等
【補助対象経費】
人件費や事業費、設備費、原材料費 等
【補助率および上限額】
・創業時準備経費
補助率:1/2以内
上限額:50万円
・事業所借入費
補助率:1/2以内
上限額:3万円で通算12ヶ月(商店街加入の場合は24ヶ月)
熊本県水俣市「水俣市創業支援事業補助金」
https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0031371/index.html
大分県中津市「中山間地域創業支援事業補助金」
【補助対象者】
中山間地域で創業する移住者あるいは定住者で、一定要件を満たす方
【申請受付期間】
〜2025年3月31日
【補助対象経費】
・工事費(事業所の新増築工事や改築工事費、ケーブルネットワーク引込工事費、屋内工事費)
・設備費(備品購入費や設備費、設備等運搬費、事業用車両購入費)
・役務費(不動産契約仲介手数料や登記手数料、広告宣伝費等)
【補助率および上限額】
・補助率:1/2以内
・補助限度額:100万円(1,000円未満切捨て)
大分県中津市「中山間地域創業支援事業補助金」
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2020040200084/
宮崎県日南市「日南市創業支援事業補助金」
【補助対象者】
・創業前の方
・日南市創業支援事業計画に位置付けた特定創業支援事業を受講した方、あるいは当該年度中に受講予定の方
・日南商工会議所や北郷町商工会、南郷町商工会いずれかの会員となり、継続的に経営指導を受ける(受ける予定である)方
・税金を滞納していない方
【補助対象経費】
人件費や起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費etc
【補助率および上限額】
・補助率:2/3以内
・上限額:30万円
宮崎県日南市「日南市創業支援事業補助金」
https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/2/3/1/1784.html
鹿児島県薩摩川内市「創業・チャレンジ支援補助金」
【補助対象者】
以下のいずれかに該当する方が対象です
・中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
・商店街全体の振興のために運営されている組合
・新たに事業を行うもの
【交付期間】
・利子:融資日が含まれる月の翌月から起算して3年
・保証料:融資日から起算して最初の12月31日
【補助対象経費】
・利子(交付期間中の毎年1月~12月の間に金融機関に支払った利子相当額
・保証料(交付期間中に支払った初年度の信用保険料相当額)
【補助率】
利子および保証料のいずれも100%
鹿児島県薩摩川内市「創業・チャレンジ支援補助金」
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1013/1/7/2/2076.html
沖縄県名護市「名護市創業支援事業計画」
【補助対象者】
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、事業を営んでいない個人あるいは事業開始日以降、5年を経過していない個人 等
【補助対象経費】
会社設立時の登録免許税 等
沖縄県名護市「名護市創業支援事業計画」
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021051400012/
創業時に申請できる融資「新規開業資金」とは
上記のように各自治体が運用している制度だけでなく「新規開業資金」も利用できます。新規開業資金とは、日本政策金融公庫国民生活事業が展開している制度です。融資となるため返済は必要ですが、多額の資金援助を受けられるため、創業初期の方は活用を検討してみてください。
【融資対象者】
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
【融資対象経費】
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
【融資限度額】
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
創業時に申請できる融資「新規開業資金」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
まとめ
日本には国や自治体が運用しているさまざまな補助金や融資制度があります。今回紹介した以外にも非常に多くの制度があるため、都内や地方で創業を考えている方は、該当地域で利用できる制度がないかチェックしておきましょう。