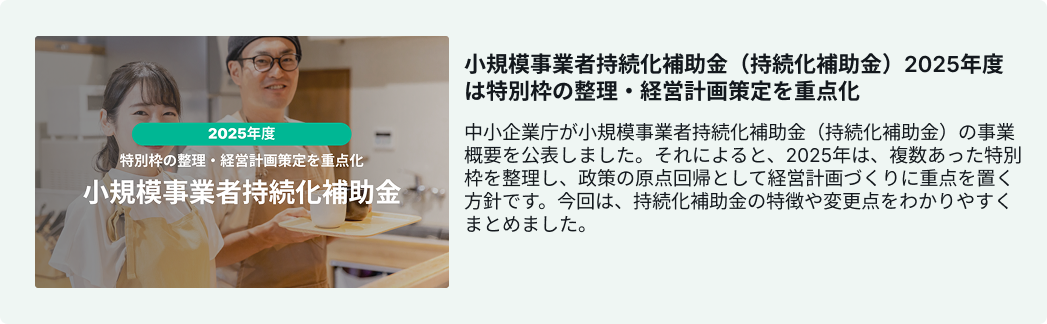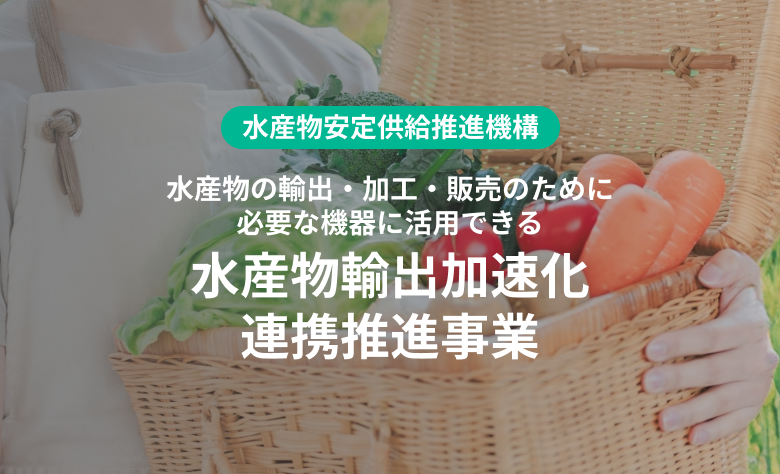
世界的に健康志向が高まり、アジアを中心に日本産の水産物への関心が高まる中、安定的な輸出体制を築くことは、水産業の持続的な成長にとって重要な課題となっています。しかし、輸出の現場では、生産から流通、販売まで、さまざまな工程で課題が山積しており、単独の事業者だけでは十分な対応が難しいのが現状です。
こうした状況を背景に、国は水産物の輸出力強化を目的とした「水産物輸出加速化連携推進事業」を立ち上げました。この事業は、関係する多様な事業者が連携し、課題の洗い出しからシステム導入・実証までを一体的に行うことで、輸出バリューチェーン全体の改善を目指します。
輸出に取り組む中で課題を感じている事業者の方は、この補助金を活用し、連携による持続可能な体制づくりをぜひご検討ください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次
水産業を取り巻く現在の課題
日本の水産業は今、大きな転換点に差し掛かっています。漁業就業者の数は年々減少し、平均年齢も60歳を超えるなど高齢化が深刻化しています。漁獲量の減少や燃料価格の高騰といった経済的要因も、漁業経営の不安定化に拍車をかけています。一方で、水産業は日本の食文化や地域経済を支える重要な産業でもあります。とくに沿岸部の漁村にとっては、漁業が地域の雇用や伝統を守る柱となっており、その持続性が問われています。
農林水産省の「令和3年度 食料・農業・農村白書」でも、水産業の衰退傾向とそれに伴う地域の疲弊が取り上げられ、ICT導入や6次産業化など、新しい発想や取り組みの必要性が指摘されています。このような背景の中で注目されているのが、水産業や漁村の活性化を支援する補助金制度です。地域の力を引き出しながら、持続可能な漁と地域づくりを実現するための一歩として、多くの現場で活用が期待されています。
水産物輸出加速化連携推進事業とは
この事業は、水産物の輸出に関わる多様な関係者が連携し、課題の共有と解決に向けた取組を推進するための支援制度です。生産者から輸出業者までが一体となって体制を構築することにより、各工程での無駄や非効率を排除し、輸出市場に向けた品質・コスト・スピードの最適化を図ることを目的としています。事業は複数の区分で構成されており、それぞれのフェーズに応じた支援が受けられる仕組みとなっています。単なる資金補助にとどまらず、調査や実証、システム導入など幅広い活動に活用できるのが特徴です。
補助率・補助額について
本事業では、事業の種類によって補助率が異なり、以下の通りとなっています。
| 輸出バリューチェーン改善検討事業 | 定額補助 |
|---|---|
| 輸出バリューチェーン改善システム等導入事業 | 1/2補助 |
| 輸出バリューチェーン改善実証事業 | 1/2補助 |
補助率は、1/2以内となっているほか、連携体制の構築や事業計画の検討・調査、コンサルティングにかかる経費については、定額(合計上限600万円以内)となっています。
また対象となる経費は、輸出体制の構築に直結する実務的なものが多く含まれています。具体的には、以下のような費用が補助対象となります。
| 事業名 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 輸出バリューチェーン改善検討事業 | (1) 輸出加速化連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査に要する経費 (2) 事業計画のコンサルティングに要する経費 |
| 輸出バリューチェーン改善システム等導入事業 | (1) 販売等電子システム導入に要する経費 (2) 水産物の加工のために必要な機器、資材(水産物の処理・加工機器、冷凍・冷蔵・貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器等)の購入費 (3) 水産物の集出荷・貯蔵・販売等に必要な機器、資材(水産物の選別機器、冷凍・冷蔵機器、検査機器、衛生管理機器、集出荷用機器、集出荷用資材、販促資材、鮮度保持容器等)の購入費 |
| 輸出バリューチェーン改善実証事業 | (1) 市場調査・商談等に要する経費 (2) プロモーション資材等の作成に要する経費 (3) 研修等の知識・技術の取得に要する経費 (4) 保管経費(水産物の冷蔵庫等での保管料) (5) 入出庫料(冷蔵庫等の入出庫料等) (6) 加工経費(新商品開発・試作に要する経費) (7) 原材料等費(試作に要する経費) (8) 運送経費等の物流構造の改善を図る取組に要する経費 (9) その他水産庁長官が必要と認めた経費 |
以下の経費は申請できないのでご注意ください。
・国等の他の補助事業による支援を現に受け、また受ける予定となっている取組に係る経費
・自力により現に実施し、または既に完了している取組に係る経費
・事業の実施期間中に発生した事故または災害のための経費
・施設整備、用地取得、借地料、補償のための経費
対象者と対象事業
補助を受けるには、必ず「輸出加速化連携協議会」の結成が求められます。この協議会は、次の3者以上で構成される必要があります(協定の締結が必要です)。
- 【必須1】生産段階事業者(例:漁業者・養殖業者・漁協など)
- 【必須2】加工・流通段階事業者(例:水産加工業者・倉庫・卸売・物流業者など)
- 【必須3】輸出段階事業者(例:商社・通関業者など)
さらに、以下のような機関を加えることも可能です。
- 地方公共団体
- 公的研究機関
- 金融機関
- 保険会社
- 交通機関
- ITベンダー
- マーケティング事業者 など
メンバーによる協議体が主導することによって、輸出体制全体の高度化と、現場目線に立った課題解決が実現しやすくなります。
対象となる取り組み、事業は以下の4つとなります。
| 新市場開拓・多角化実証支援 | 既存輸出先に加え、新たに非日系市場や第三国への輸出拡大にチャレンジする取組 |
|---|---|
| 供給力拡大・革新的鮮度保持技術実証支援 | 輸出に至るまでの輸送能力低下による鮮度低下、活魚致死率低下等の課題解決を図りつつ輸出拡大にチャレンジする取組 |
| 水産物輸出規制等対応実証支援 | 生産から輸出までの流通情報管理や加工体制整備により、輸出先国等の規制や調達基準に対応しうる輸出体制の構築による輸出拡大の取組 |
| 新規参入実証支援 | 現地ニーズを独自に調査し、競合を避けつつ小ロットから段階的に新規輸出にチャレンジする取組 |
申請スケジュール
申請受付期間は、2025年3月10日(月)から5月7日(水)までです。
約2か月の期間が設けられていますが、協議会の設立や協定書の取り交わし、事業計画の作成には時間を要するため、早めの準備が欠かせません。
各構成員との役割や方針をすり合わせながら、必要書類の整備や体制づくりを同時に進めていくことが、スムーズな申請につながります。
この補助金の魅力と活用メリット
「水産業・漁村活性化推進機構」が実施する本補助金制度は、水産業の現場が抱える多様な課題に対応できる柔軟な支援内容が特長です。
たとえば、地元で水揚げされた魚介類を活用した新商品の開発、水産物の加工に必要な機器の導入、販売管理や輸出支援のための電子システムの整備など、実情に即した幅広い取り組みが対象となります。
さらに、地域内の他産業との連携を促す側面もあり、地域全体の活性化につながる仕組みとしても注目されています。水産業の担い手不足や高齢化といった長年の課題に対し、具体的な対策を後押しする制度として、現場にとって実効性のある支援策といえるでしょう。
まとめ
水産物の輸出を持続的に拡大していくには、生産・加工・輸出の各段階を担う事業者が密接に連携し、輸出バリューチェーン全体を最適化する体制を構築することが欠かせません。本補助金は、その実現に向けて「輸出加速化連携協議会」を組織し、共同で輸出課題の解決に取り組む団体を支援する制度です。
協議会には、生産者・加工流通業者・輸出業者の3者が参加する必要があり、地方公共団体や研究機関、機器メーカーなどの参画も可能です。水産物の輸出に意欲のある事業者は、この機会を活かして取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する